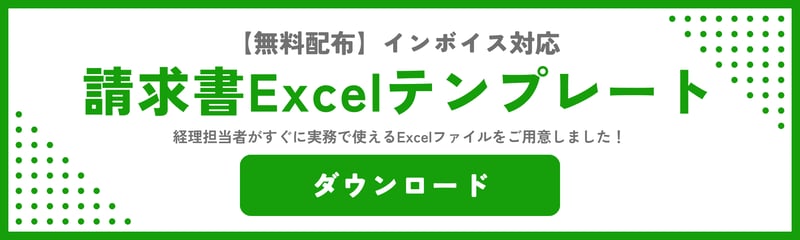取引先からの入金が遅れると、「催促しにくい」「関係性が悪化しないか不安」といった悩みを抱える事業主の方は少なくありません。しかし、請求書の未払いを放置することは、自社の経営基盤を揺るがす重大な問題に発展しかねません。
この記事では、請求書の催促が必要となる理由から、失礼にあたらない適切なタイミング、具体的な催促の手順、メールや電話の文例、さらに法的な注意点までを網羅的に解説します。キャッシュフローを守り、健全な取引を継続するための知識を身につけましょう。
請求書の催促が必要な理由と適切なタイミング
・キャッシュフローへの影響
・相手先の失念
・催促の目安
請求書の催促は、自社の経営を守るために不可欠な業務です。なぜ必要なのか、いつ始めるべきかを解説します。
未入金がキャッシュフローに与える影響
売上が計上されても、実際に入金がなければ資金は増えません。
未入金が続くと、仕入れ費用や従業員の給与、経費の支払いが滞り、最悪の場合、黒字倒産に至るリスクもあります。
健全なキャッシュフローの維持は、事業継続の生命線です。
相手先の支払い忘れ・経理ミスの可能性
入金が遅れる理由は、必ずしも悪意があるとは限りません。
「請求書が届いていない」「経理担当者が見落としていた」「振込処理を忘れていた」など、単純なミスや失念であるケースも非常に多いです。
催促は、こうした相手方のミスに気づかせる機会にもなります。
催促を開始すべき「支払期日後」の目安
催促のタイミングは非常に重要です。
まずは支払期日の翌営業日〜3営業日以内に、入金が確認できていない旨をソフトに連絡するのが一般的です。
「行き違いでしたら申し訳ありません」といった形で、あくまで「確認」として連絡することで、相手に心理的負担をかけずに済みます。
請求書を催促する手順(ステップ別)
・ステップ1:事実確認
・ステップ2:ソフトな確認
・ステップ3:書面送付
・ステップ4:法的措置検討
感情的にならず、段階を踏んで冷静に対応することが求められます。催促の基本的なステップを見ていきましょう。
ステップ1:自社の入金状況と請求書控えの再確認
催促の前に、まず自社の確認を徹底します。
相手のミスと決めつける前に、自社の不備を疑うことがビジネスマナーです。
- 入金履歴(別名義での入金、同姓同名、金額間違いがないか)
- 請求書控え(請求日、支払期日、金額、送付先住所・担当者に誤りがないか)
- 請求書の送付履歴(メール送信履歴、郵送記録)
ステップ2:メールや電話でのソフトな確認
自社に不備がないことを確認したら、担当者レベルで連絡を取ります。
最初はメールでの確認が主流です。記録が残るため、後々のトラブル防止にも役立ちます。
メールに反応がない場合や、期日から1週間以上経過した場合は、電話で直接確認することも有効です。
ステップ3:催促状(書面)の送付
メールや電話で連絡しても入金がない、または連絡が取れない場合、次の段階に進みます。
「催促状」または「督促状」といった表題の書面を、普通郵便または簡易書留で送付します。
これにより、会社として正式に対応しているという意思を伝えます。
ステップ4:法的措置の検討開始
催促状を送付してもなお反応がない場合、最終手段として法的措置を検討します。
内容証明郵便の送付、支払督促、少額訴訟など、具体的な手続きに入る前に、まずは弁護士などの専門家に相談することを推奨します。
催促の方法別文例(メール・電話)
・初回メール文例
・催促メール文例
・電話での話し方
催促は、伝え方一つで相手の受け取り方が大きく変わります。関係性を壊さないための具体的な文例を紹介します。
【メール】初回(支払期日直後)の確認文例
件名:【ご確認】お振込みの確認につきまして(株式会社〇〇)
本文:
株式会社△△ 経理ご担当者様
いつもお世話になっております。
株式会社〇〇の(自分の名前)です。
〇月〇日付でご請求いたしました「(請求書No. xxx)〇〇の件」につきまして、
本日(〇月〇日)時点でご入金の確認が取れておりません。
請求書:No. xxx
金額:xxx,xxx円
支払期日:〇月〇日
本メールと行き違いでお手続きいただいておりましたら、何卒ご容赦ください。
恐れ入りますが、現在の状況(またはご入金予定日)を
ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【メール】2回目以降(催促)の文例
件名:【再送・ご確認】〇月分ご請求のお振込みにつきまして(株式会社〇〇)
本文:
株式会社△△ 経理ご担当者様
お世話になっております。
株式会社〇〇の(自分の名前)です。
先般(〇月〇日)にご連絡いたしました「(請求書No. xxx)〇〇の件」につきまして、
再度ご確認させていただきたくご連絡いたしました。
支払期日(〇月〇日)を過ぎておりますが、
その後の状況はいかがでしょうか。
(※前回連絡への返信がない場合)
行き違いや何らかのトラブルも考えられますので、
大変恐縮ですが、本メールにご返信いただけますと幸いです。
請求書を再送付いたしますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
【電話】高圧的にならない話し方と確認事項
電話では、感情的にならず、事務的に事実を確認する姿勢が重要です。
「恐れ入りますが」「失礼ですが」といったクッション言葉を使い、高圧的な印象を与えないよう注意します。
確認すべき事項は以下の通りです。
- 請求書が届いているか
- 支払い処理の状況(手続き中か、漏れているか)
- (支払いが漏れていた場合)いつまでに入金可能か
請求書を催促する際の法的注意点とビジネスマナー
・言葉選び
・違法な取り立て
・遅延損害金と時効
催促行為もビジネスの一環です。法律とマナーを遵守し、トラブルを未然に防ぎましょう。
相手との関係性を維持するための言葉選び
催促の目的は、未収金を回収することであり、相手との関係を断絶することではありません。
「支払いを忘れている」と決めつける表現は避け、「ご確認ですが」「行き違いでしたら」といった謙虚な姿勢を見せることが大切です。
特に継続的な取引先に対しては、細心の注意を払う必要があります。
深夜早朝の連絡など違法となる取り立て行為
債権の回収であっても、度を超した行為は違法となる可能性があります。
貸金業法で規制されているような、社会通念上不適切とされる時間帯(例:午後9時~午前8時)の電話や訪問は避けましょう。
また、大声を出したり、脅迫的な言動をとったりすることは厳禁です。
遅延損害金の請求可能性と時効の確認
契約書や利用規約に遅延損害金に関する定めがあれば、請求することが可能です。定めがない場合でも、法定利率(商事債権の場合は年6%、2020年4月以降は年3%の変動制)に基づき請求できます。
ただし、実際に請求するかは相手との関係性によります。
また、債権には時効(原則5年)があるため、長期間放置しないよう注意が必要です。
催促しても入金がない場合の次のステップ
・内容証明郵便
・支払督促
・弁護士相談(少額訴訟)
通常の催促で効果がない場合、より強制力のある法的手段を検討します。
内容証明郵便による催告書の送付
内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に送ったか」を郵便局が証明するサービスです。
法的な強制力はありませんが、「支払わなければ法的措置も辞さない」という強い意思を相手に伝え、心理的圧力を与える効果があります。
また、時効の完成を6か月間猶予させる「催告」としての効力も持ちます。
支払督促(簡易裁判所の手続き)
支払督促は、簡易裁判所を通じて行われる法的手続きです。
申立てが受理されると、裁判所から相手方に支払督促が送付されます。相手方が2週間以内に異議申し立てをしなければ、仮執行宣言を得て強制執行(差押えなど)が可能になります。
書類審査のみで完結するため、通常の訴訟よりも迅速かつ低コストです。
弁護士への相談と法的措置(少額訴訟など)
相手が支払督促に異議を申し立てた場合や、状況が複雑な場合は、弁護士への相談が不可欠です。
弁護士から相手に連絡(弁護士照会)してもらうだけで、態度が軟化し支払いにつながるケースもあります。
最終手段としては、60万円以下の金銭請求に使われる「少額訴訟」など、本格的な訴訟手続きに進みます。
まとめ
・請求書催促の重要ポイント
・早期対応と毅然とした態度
請求書の催促は、自社のキャッシュフローを守るための重要な業務です。最後にポイントを振り返ります。
請求書催促の重要ポイントの再確認
本記事で解説した重要なポイントは以下の通りです。
- 未入金はキャッシュフローを悪化させ、経営リスクとなる。
- 催促は、まず自社の確認から始める。
- 初期段階(期日後すぐ)は「確認」としてソフトに連絡する。
- メール、電話、催促状、法的措置と段階的に対応を強化する。
- 催促時もビジネスマナーと言葉選びを遵守し、違法な取り立ては行わない。
- 最終的には弁護士や裁判所の手続きも視野に入れる。
早期対応と毅然とした態度の重要性
請求書の未入金問題において最も重要なのは、「早期対応」と「毅然とした態度」です。
支払期日を過ぎたらすぐにアクションを起こし、相手に「支払いを後回しにしても大丈夫」という印象を与えないことが肝心です。
本記事で紹介した手順と文例を参考に、大切な売掛金を確実に回収し、健全な事業運営を目指しましょう。